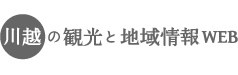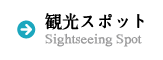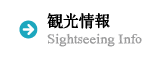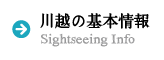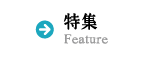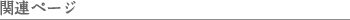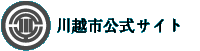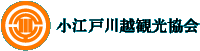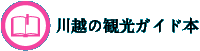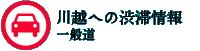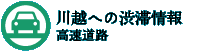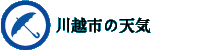トップページ > 文化財 > 有形文化財 > 東照宮 本殿付宮殿

東照宮本殿は、三間社流造・銅瓦本葺・極彩色。
創建は寛永10年(1633)。その5年後の寛永15年の大火で炎焼失し、寛永17年に再建されています。棟札によれば、願主 家光、奉公 堀田正盛、大工 木原義久、 導師 天海僧正とあります。
本殿に安置されている宮殿(円形厨子)は、高さ2尺5寸(76cm程度)で、中には家康公の木造が祀られています。その姿は、甲冑を着け右手には槍、駿馬に騎っています。この木造は家康の遺骸を、ここ喜多院で法要を上げた喜元和3年(1617)に天海が彫作したものです。
創建は寛永10年(1633)。その5年後の寛永15年の大火で炎焼失し、寛永17年に再建されています。棟札によれば、願主 家光、奉公 堀田正盛、大工 木原義久、 導師 天海僧正とあります。
本殿に安置されている宮殿(円形厨子)は、高さ2尺5寸(76cm程度)で、中には家康公の木造が祀られています。その姿は、甲冑を着け右手には槍、駿馬に騎っています。この木造は家康の遺骸を、ここ喜多院で法要を上げた喜元和3年(1617)に天海が彫作したものです。
参考:川越の文化財(川越市教育委員会)、現地案内板より
*本殿の内部見学をすることは出来ません。
| 名称 | 東照宮 本殿付宮殿(円形厨子) |
|---|---|
| 指定 | 国指定 重要文化財 建造物 |
| 員数 | 1 |
| 所在地 | 埼玉県川越市小仙波町1-21-1 |
| 所有者 | 東照宮 |
| 指定日 | 昭21.11.29 |