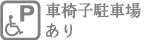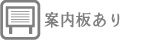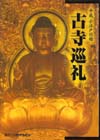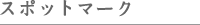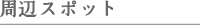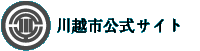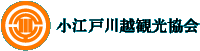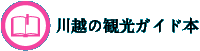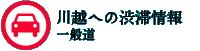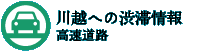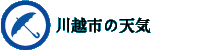トップページ > 観光スポット > 見る > お寺 > 中院


「天台宗別格本山」「関東八箇檀林」「狭山茶発祥の地」「創健1100余年の古刹」・・・
中院を象徴する肩書きは、枚挙に暇がありません。長い歴史と共に、山門から伝わる雰囲気は風格があり、荘厳な佇まいです。
しかし一歩境内へ入ると、不思議とかしこまった印象は受けず、どこか親しみ易い感じがします。それこそが中院のお人柄ならぬお寺柄なのです。
中院の歴史
中院の歴史は、平安時代まで遡ります。
天長年間(824~833)、この地に3つの寺、星野山無量寿寺「仏蔵院」「仏地院」「多聞院」が次々と創健されました。
仏蔵院(北院)は後の喜多院、そして仏地院こそ現在の中院です。多聞院(のちに南院)は明治に入り廃寺となりました。これら3院で構成されたのが星野山無量寿寺です。現在は喜多院が境内も広く勢いがあるイメージですが、当時は中院が中心的役割があり、勢力を持っていました。
そんな中院の見どころは、「静かで趣のある境内」と「四季折々の風景」です。
中院の見どころ
中院、花の移ろい
中院の行事・イベント
中院の略歴
| 天長7年(830 / 平安時代) |
慈覚大師円仁により創建。 淳和天皇の勅許により芳道仙の古跡を起こし一寺を建立。星野山無量寿寺仏地院の勅号を賜る |
|---|---|
| 天慶4年(941 / 平安時代) | 平将門の天慶の乱に遭い寺運衰退 |
| 永仁4年(1296 / 鎌倉時代) | 尊海・成田氏の助けにより仏地院を再建。 関東天台の教寺580余が、全てが仏地院(中院)に属す。関東天台の本山の勅許を得る。 |
| 天文 6年(1537 / 室町時代) | 後北条氏 vs 上杉氏の戦いにより全てを焼失 |
| 寛永 9年(1632 / 江戸時代) | 尊能が再び盛んにする。 |
| 寛永15年(1638 / 江戸時代) | 川越大火で類焼。 |
| 寛永16年(1639 / 江戸時代) | 幕府の命令により、現在地に移転(東照宮造営の為) |
| 寛永19年(1733 / 江戸時代) | 本堂が再建。 |
| 昭和19年(1944) | 釈迦堂が焼失。 |
| 昭和33年(1958) | 中院が川越市の史跡に指定される。 |
| 昭和51年(1976) | 天台宗務庁より「天台宗別格本山特別寺」の称号をもらう。 |
| 昭和61年(1986) | 釈迦堂が古い天台様式によって再建。 |
| 平成4年(1992) | 島崎藤村ゆかりの「不染亭」を新富町より移築。 |
スポット詳細
| 名称 | 中院(なかいん) |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県川越市小仙波町5-15-1 |
| WEB | http://www.kawagoe.com/nakain/ |
| 時間 | - |
| 休み | なし |
| 料金 | 無料 |
| 所要時間 | 5分~15分 |
| 駐車場 | あり(無料) |
| 指定 | 川越景観百選: 中院 市指定史跡: 中院 |
中院について
| 名称 | 中院 |
|---|---|
| 宗派 | 天台宗 |
| 本尊 | 阿弥陀如来 |
| 創建 | 天長7年(830 / 平安時代) |
| 開山・開基 | 開山: 慈覚大師円仁(えんにん) |
| 建物・仏像等 | 本堂 山門 鐘楼門 釈迦堂 不染亭 狭山茶発祥の地の碑 島崎藤村義母の墓 成田山開山上人の墓 太陽寺一族の墓 釈迦堂大先達の墓 |
| 文化財 | 市指定史跡: 中院 |
| ご利益 | - |
| 年中行事 | 8月: 法灯花 12月31日: 除夜の鐘 |
| 札所・霊場 | - |
| ご朱印 | あり |
アクセス
| 関越自動車道「川越IC」より | 13分 |
| 圏央道「狭山日高IC」より | 35分 |
| 西武新宿線「本川越駅」より | 14分 |
| 東武東上線・JR川越線「川越駅」東口より | 16分 |
| 東武東上線「川越駅市」より | 24分 |
| 駅 | バスの種類 | 系統 | 下車するバス停 | 徒歩 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東武東上線「川越駅」東口, JR川越線「川越駅」東口, 西武新宿線「本川越駅」 | 西武バス | 本52 | 喜多院入口バス停 | 4分 |
| 2 | 東武東上線「川越駅」西口, JR川越線「川越駅」西口, 西武新宿線「本川越駅」 | 小江戸巡回バス | 中院バス停 | 1分 | |
| 3 | バス停 | 分 |
掲載の観光・地域スポット情報は2011年10月現在のものです。現在の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
» 中院についてのコメントや、口コミ、おすすめ情報などがあれば、下記より投稿することが出来ます。お気軽にどうぞ。(*メールアドレスは表示されません。)

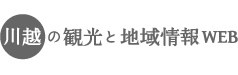




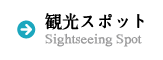
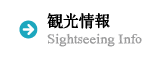
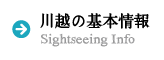
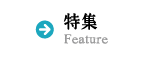

















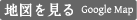
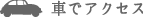
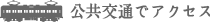



 正面入口は段差があるので、北・南側から入場。
正面入口は段差があるので、北・南側から入場。